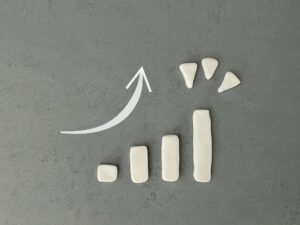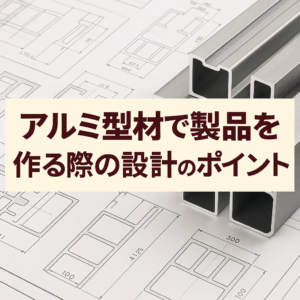アルミ型材の『見えない進化』──設計段階で差がつくポイントとは?
本文執筆
アルミ型材は一見シンプルな直線形状が多く、どれも似たように見えるかもしれません。しかし、実際には「見えない部分」に設計者とメーカーの工夫が凝縮されています。設計初期段階での選定・仕様検討の有無が、後の施工性・コスト・耐久性に大きく影響することも少なくありません。本稿では、建築・建材向けアルミ押出型材の設計における注目すべきポイントを解説します。
1. 「形を変える」でなく「機能を内包する」断面設計
アルミ押出型材の魅力は、自由度の高い断面形状にあります。しかし、単なる見た目の変化ではなく、内部に機能を持たせる設計が増えています。
たとえば、空気の流れを制御するためのチャンバー構造、電気配線を内蔵できる空洞、雨水を誘導するドレンチャンネルなど、内部構造に意味を持たせた設計が進化しています。これにより、別途金物を追加する必要がなくなり、施工性・コスト・仕上がりの美しさにも貢献します。
2. 強度と軽量化のバランス設計
アルミは軽量で加工性に優れていますが、その一方で十分な強度を確保するための設計が不可欠です。
近年では、断面形状を工夫してリブ(補強肋)を設けたり、応力集中を避ける曲線部を採用したりするなど、構造解析に基づいた設計が一般化しています。構造部材としての機能を持たせながらも、極力無駄な肉厚を省き、材料コストと重量の最適化を図る工夫が随所に見られます。
3. 表面処理が左右する「耐久性と印象」
アルミ型材の耐候性や美観は、表面処理に大きく依存します。代表的な処理方法には、アルマイト処理(陽極酸化)やフッ素焼付塗装などがあります。
屋外用途では耐紫外線性や腐食耐性、屋内では手触りや色調の高級感が求められます。設計段階で仕上げ処理の種類を選定することにより、メンテナンス周期や長期コストにも差が出てきます。
4. メーカー任せにしない「設計者との協働」が鍵
意外と見落とされがちなのが、設計者と押出メーカーの早期連携です。特に新規プロファイルを設計する場合、型代、押出方向、抜き勾配、切削後の公差など、メーカーの技術的な制約や知見を設計段階から取り込むことで、後戻りのないスムーズな立ち上げが可能になります。
最近では、BIMやCADデータを共有しながら協働設計を進める事例も増えており、「見えない部分の擦り合わせ」が製品の完成度を高める重要な要素となっています。

お問い合わせ
ご依頼及びサービス内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください